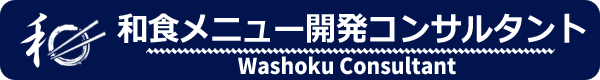飲食店の原価コントロールと原価率を徹底解説
2025年1月29日更新
飲食店にとって
二大変動費である原価と人件費。
コントロールできるかどうかで
お店の利益は大きく変わります。
コンサルティングでお話する際、
意外に原価も人件費もコントロール
できておらず悩んでいる飲食店多いです。
いろいろな人が
原価のコントロールについて
書いております。
かなりの長文ですが今回の記事さえ
読めば原価をコントロールする上での
ポイントは全て網羅する内容となっております。
是非お読みいただき、
自店舗の原価コントロールにお役立て
ください。
原価とは?原価率とは?
まず原価と原価率について
定義を知っておきましょう。
原価とは、
商品が出来上がるまでにかかる経費です。
食材はもちろんのこと
包装資材の価格も含まれます。
揚げ物でしたら揚げ油、
お弁当でしたらパックも入ります。
もちろん、調味料も入ります。
一方で、原価率とは、
原価率
= (期首棚卸し高+期中仕入高-期末棚卸し高) ÷ 売上高 × 100
この公式を覚えて下さい。
業種業態によりますが、
飲食店のコストは人件費、原材料費、
諸経費、初期条件、本部費等からなります。
一般的には、
- 人件費30%
- 原料費30%
- 諸経費15%
- 初期条件、本部費合わせて20%
で経常利益が5%残る感じです。
この枠組を基本として経費を抑えます。
現在人件費も原料費も高騰しています。
原価コントロールできているかどうかは
あなたの飲食店の利益に直結します!
だからこそ
原価コントロールは重要
なのです。
もっと言えば、
原価コントロールをした原価率こそ、
料理長の通信簿なのです。

飲食店で原価率が30%だと言われる理由
『原価率30%』はあくまでも
一般的な数値です。
もちろん、
1つ1つのメニューの原価率は
違います。
ドリンクとフードでも違います。
業態でも違います。
私の主たる業種の
和食店の場合はドリンク比率が15~20%、
居酒屋の場合は25~35%位でしょうか?
居酒屋では、
1人ドリンクを含めて5.5品注文をされます。
海鮮居酒屋でしたら、
海鮮メニューは、40%前後だと思います。
集客の目玉商品は35~40%ですが、
オリジナル商品が20%前後なので、
これを売り抜いて粗利ミックスで33%
にしています。
尚、弊社の料理長研修では、
かにまんじゅう、ホタテのもろこし焼き、
力どり、わさびステーキ等
上記丘里の名物商品をレシピを添えて、
全てお伝えしております。
更なる利益を追求すべく、
仕入れの見直し、包装資材の変更、
そして販売促進費合わせて4%の削減
に今期丘里は取り組んでいます。

理論原価率と実際原価率を知る
原価率を考える際には
1、理論原価率:理論上の原価率
2、実際原価率:営業していて実際にかかった原価率
が存在します。
この理論原価率と実際原価率が同じ
であれば一番良い訳です。
実際には許容範囲があります。
差異が少ないほど良いですが、
まずは1%を目標としてください。
最終的には0.8%以内を目指します。
これには以前お伝えした
ロス管理の精度と仕組みの構築
が必要となります。
賄い材料費は、
出来れば原材料費から控除する
と良いですね。
クレーム処理、オーダーミス、提供ミス
など明確なロスは毎日記録して原材料費
から控除して雑損処理します。
食材ごとの歩留まりを明確にして、
メニュー基準表の精度を高くする
ことも大切です。
食材の単価も変わったら、
修正をしていきましょう。
仕入れ単価もそうですが、
歩留まりと物理的不可避ロスも明確にして、
反映させていきます。
こう考えると料理人の感に頼ることなく、
1つ1つ見直す必要がありますね。
特に食材費や包装材費、更に人件費の高騰
をしている昨今ですから、
改めて原料費管理は重要になってきています。

画像はイメージ(写真ACより)
原価を下げるための6つのポイント
では実際に原価を下げる際のポイントを
6つご紹介します。
どれも大切なポイントですので、
しっかり抑えて下さい。
ロスを減らす
まず原価を下げるには、
ロスを減らすことは必須です。
ロスについては
詳しく書いて記事がありますので、
そちらをご覧ください。
仕入れを工夫する
買う場所として、
市場、スーパー、道の駅などありますが、
野菜ですと鮮度、価格を考慮すると、
スーパーがオススメです。
いかに大量に仕入れて
長期保存できる方法を確保するか
がポイントです。
大量に仕入れれば安くなりますから。
魚なんかは
市場に行けばお買い得品があります。
もしあなたが数店舗お店を持っているなら、
1つの店舗で仕入れたものを仕込んで、
仕込んだ状態で各店舗に配達する
そうすれば
仕込み時間の削減と原価を下げる
の両得になります。
仕入れた魚を桶に入れて、
お客様に見せれば喜んで、
注文してくれます。
また大量に仕入れたものは、
3D冷凍庫で保管すればよい状態で
長期保管できます。
この保管していたものに、
そのときに仕入れた生の海鮮ものを
一緒にして出せばお客様も喜びます。
道の駅は意外と高かったりしますので、
市場に頻繁に行って価格動向を見て、
何ができるのか考えることです。
ムダがなければ原価率は下がります。

画像はイメージ(写真ACより)
食材ごとの歩留まり率を抑える
仕込み後の産出数量です。
これは歩留まり率で表します。
この歩留まり率は、
野菜など季節によって品質のばらつきがあり
変化するものもあります。
誰が仕込みをしても、
同じようになるような手順が必要
となります。
例えばキャベツ。
外側の1枚をはがして仕込みするものを
人によって3~4枚むいて仕込みする人が
いると歩留まりが悪くなります。
廃棄するような部分は、
佃煮、炒め煮、ふりかけ、香り塩等
に使って商品化する等をやっています。
これは料理長の利益に対する執念です。
季節ごとに、
1つ1つ歩留まり計算をすることを
お勧めいたします。
更にキャベツの場合、
外側の葉1枚と芯の部分を除いた量
が実際のキャベツの重さになります。
元のキャベツの85%位になるでしょう。
この基準も食材によって作る必要があります。
原価率の意識を高めるためにも
各自が1人前いくらか?という意識
を高めていくことが大切になります。
外部からの加工された食材を使うか、
人件費をかけて原価を押さえていくのかは、
会社の判断になります。
食材によりますが私としては
マニュアルをきちんと作ることでスタッフ
が仕込みをすることをお勧めします。
そのためには意識改革が重要です。
どんなに良いマニュアルがあっても、
スタッフ1人1人の食材に対する愛情と
時間を惜しまず丁寧な仕事が重要なのです。
人件費が毎年上がっている今日
とても悩ましいところですが、
重要なポイントだと思っています。

仕込み数のコントロール
重要な調理作業を
パート、アルバイトスタッフに任せきり
にしていませんか?
量と仕込みの種類は誰が決めていますか?
原材料費がかなり上昇している今において
とても重要なポイントです。
曜日や時間帯の売上げ予測に応じて、
調理場の責任者が指示を出すべきです。
売上予測が正確でなければ無駄が生じます。
日報等で、
3年間の同じ週の同じ曜日や時間帯を参考
に仕込みをしましょう。
提供時間を考えて
仕込んで置くものを決めておきます。
しかし、
とんかつ屋でとんかつを予め揚げておく
寿司屋で予め握っておくとはNGです。
客単価の低い立ち食いそば屋等では、
天麩羅の揚げおき等あっても良いと
思います。
しかし普通の和食店やそば店では、
その都度揚げた方が良いでしょう。
先ほどの揚げおきに関しても
揚げすぎはいけません。
しっかり出数を予測してください。
時間と共に劣化してしまいます。
社内での基準が必要です。
仕込みチェック表も必要ですよ。
仕込みチェック表があれば、
ことを防げます。
絶対仕込みチェック表は作成して
設置しておきましょう。
在庫管理の注意点として、
食材は味と量を調べることが重要です。
品質に自信がないものは使用しないことです。

納品時の検品のルール化
お店に食材が納品されるとき、
誰がどのように立ち会っていますか?
検品とは、
品物の質及び個数、量を検査すること。
検収とは、
納品書や発注書から現品の照合をすること。
現品を照合する際には
品名、数量、規格や品質を照合して、
チェックに合格した品物を収納します。
不良品があれば処理までする
この一連の作業を検収と言います。
検品と検収は
品質維持のために非常に重要ですので、
きちんと時間を確保する必要があります。
そのためには、
業者の搬入時間を決めておくと良いでしょう。
美味しい料理を提供するには、
食材において規格、品質、産地が決まります。
これは、店の会社のこだわりです。
店舗で扱う食材の収納、保管に関しては、
一覧表にまとめて周知徹底をします。
また
・先入れ先出しの徹底
・食材への賞味期限の明記
・食材の温度管理
も重要です。
冷蔵庫及び冷凍庫の温度管理チェックは、
最低開店前、夜営業前、閉店後の3回は
必要となります。
食材の冷凍庫や冷蔵庫への入れ過ぎは
効きが悪くなる原因になりますので、
70%位に抑えましょう。
機器の故障等で
食材を劣化させてしまえば、
大量ロスになってしまいます。
納品書の取り扱いも大切
納品書の取り扱いも大切です。
仕入れ合計のミスを防ぎ、
買掛金とのズレもなくなります。
納品書は、
1業者、2店、3本部の三部
があるとよいです。
業者ごとの仕入れ集計表は必須です。
「累計仕入率」
= 毎日の仕入高累計額 ÷ 累計売上高
も毎日出していきましょう。
検収作業の手順として、
発注した食材が全て納品書に記載されているか?
数量と納品書の数量は一致しているか?
重さが決められた基準になっているか?
納品された時の荷姿と状態に異常はないか?
をチェックします。
チェックのためには前提条件として、
食材ごとの規格基準(こだわり)を
会社で作ることも必要になってきます。

原価基準表を作る
制度の高い原価基準表を作りましょう。
過去3年間の売上から、
客数、売上予測を95%~105%の正確な数値
が出せるようにします。
そのためには、
責任者が常に考えながら仕事をする事
が大事です。
原価基準表の例を含め、
弊社の料理長研修では飲食店経営に
必要な帳票もお渡ししております。
ご活用ください。
私がこだわる原価を下げるための更なる3つのポイント
一般的に原価を下げるポイントとして、
の6つをお伝えしました。
しかし更にレベルアップしてもう3つ
私のこだわりポイントをお伝えします。
正直有料情報にしたいくらいの内容です(笑)
毎月の厳密な棚卸し
飲食店の原価管理において
棚卸しはとても重要です。
あなたのお店の冷蔵庫や冷凍庫に、
何ヶ月も眠っている食材ありませんか?
毎月の原価率を出すことも目的ですが、
動いてない在庫商品と量を料理長店長が
把握することがまず大切です。
把握することで翌月に完全に使いきる、
売り切ることがとても大切なのです。
棚卸しは丁寧にやれば時間がかかります。
しかし、
在庫量が少なければ数も数えやすくなり、
時間もかかりません。
在庫量が多ければ財務状態は悪くなります。
飲食店は鮮度を売ってるわけですから、
なるべく在庫を持たないようにしておく
ことが重要です。
目標の期末在庫金額は、
3日分の売上げ金額が理想です。
あなたのお店の期末在庫金額はいくらですか?
原価にこだわったメニュー開発
冷凍庫や冷蔵庫に眠っている食材を
活かしてメニュー開発ができるかは
とても大切です。
これには
ホールスタッフの協力が絶対に必要
なのです。
丘里では、
鯛のかぶと煮が名物商品で売り筋商品
になっております。
一週間で100個売れます。
ぶりのかま煮付けも、
一週間で30個前後売れます。
どちらも800円です。
刺身を扱っていると
どうしても中落ちや頭が残ってしまいます。
色の変わったマグロ、カンパチ、鯛等です。
これを私は塩焼きにせず、
煮付けにして鍋ごと店頭において、
来店時に必ず商品を案内してもらって、
お客様に買っていただいてます。
先日もマグロのかまを1個200円で仕入れて、
800円で販売してもらいました。
120分で9個完売です。
ぶりのかま煮付けも6人前90分で完売です。
冷凍庫に眠っている食材を商品化して
販売することで冷蔵庫や冷凍庫の中が
スッキリします。
在庫量は減り棚卸しも楽になり、
正に一石二鳥です。
売り切る説明力
名物商品にして、
女将が売り抜いているのです。
どうやって作るのか?
どうやって売り抜くのか?
秘密があります。
こればかりは、
こちらのブログでは書ききれませんので、
弊社開催の1日研修や女将研修や幹部研修
でしっかりお伝えします。

を盗んでください
原価率をコントロールするためには
飲食店の商品は、
感動レベルの商品作りがなければ、
繁盛の継続と拡大はありません。
この感動レベルの商品作りは、
職人芸の味だけに頼ってはなりません。
一番大事なことは、
会社が求める基準通りの調理ができ、
利益をしっかりあげることです。
これは原材料管理に関する知識と技術
がなければ継続できません。
原価率をコントロールする上で、
数字に強くなくても常に数字を
気にすることが大切です。
私が指導している限り、
とかく料理人は数字が苦手という
方が多いです。
私達は飲食業を通じてお客様を喜ばせ、
私達自身も幸せな人生を送れるように
日々努力しております。
つまり
お互いがウィンウィンになるため
に仕事をしているのです。
儲けだけ考えていても、
利益の継続や事業の拡張はありません。
数値管理の基本は、
今日やることは今日中に終わらせるです。
飲食店経営者の方々が
プロ意識を持って数値を常に意識し、
執念で数値を叩き出して行くことが大事
だと痛感してております。
私と一緒に飲食店を盛り上げていきませんか?
ご興味のある方は弊社の1日研修をご活用ください。
絶対何らかの経営のヒントを得られるはずです!
この記事を書いた人

- フードスクエアカンパニー代表
- 丘里グループは創業50周年を迎えることができました。食を通じて「喜び、幸せ、そして感動」をモットーニ「人」の魅力で他の飲食店と差別化を図り、地元茨城県古河市でナンバーワン企業であり続けることを目指しております。
最新の記事
 人材育成2023年7月27日料理人に必要なスキルは料理だけではなくビジネススキル及び経営力も必要
人材育成2023年7月27日料理人に必要なスキルは料理だけではなくビジネススキル及び経営力も必要 人材育成2023年6月28日飲食店はコンテストを活用してスタッフを育成しよう
人材育成2023年6月28日飲食店はコンテストを活用してスタッフを育成しよう 経営2023年6月7日地方の飲食店の出店戦略と物件を探す際のチェックポイント
経営2023年6月7日地方の飲食店の出店戦略と物件を探す際のチェックポイント 集客2023年5月17日飲食店でイベントを開催して集客しましょう
集客2023年5月17日飲食店でイベントを開催して集客しましょう
丘里の全てがわかる1日研修のご案内
丘里の全てがわかる『丘里1日研修』を
開催しています。
実際に店舗に入り、
私はもちろん女将の話も聞ける
充実の研修です。
詳細は以下のボタンよりご覧ください。